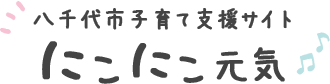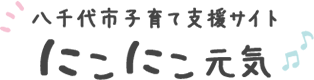本文
令和6年度 児童手当制度改正のご案内(令和6年10月分から)
制度改正により変更となるのは、令和6年10月分からです。
初回支給は令和6年12月13日(金)で、2か月分(10月・11月分)を支給予定です。
- 新たに受給できるようになる人は、申請が必要となります。
対象の方には、8月下旬に申請書を送付しました。(公務員の方は勤務先に申請してください。) - 児童手当を受給中の人は、原則申請は不要です。(一部の方は申請が必要となる場合があります。)
- 制度改正に関すること以外は、「児童手当のご案内ページ」をご確認ください。
目次
1 制度改正の概要
2 改正後の児童手当の額
3 スケジュール
4 必要な手続き
(1)制度改正により新たに手当を受給できるようになる人(申請が必要)
(2)児童手当を受給している人(原則申請不要)
19歳~22歳となる年度の子を含め、3人以上の子がいる人
1 制度改正の概要
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により児童手当法が一部改正され、令和6年10月分から児童手当が以下のとおり改正されました。
なお、改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月(10月・11月分)となります。
| 改正内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 支給対象が高校生年代まで拡大 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 2 | 所得制限が撤廃 | 所得制限限度額を超えると月額5,000円に減額(特例給付) 所得上限限度額を超えると支給対象外 |
所得制限なし |
| 3 | 第3子以降の手当額及び対象の拡大 | 3歳~小学校修了までの第3子以降について月額15,000円 |
出生~高校生年代(18歳の年度末まで)の第3子以降について月額30,000円 |
| 4 | 多子加算のカウント対象の見直し | 高校生年代(18歳の年度末まで)の監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児童の手当額が増額 | 22歳の年度末までの監護する子をカウントし、第3子以降の支給対象児童の手当額が増額 |
| 5 | 支払期月の増加 | 年3回(2月、6月、10月) (前月までの4か月分を支払) |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) (前月までの2か月分を支払) |
また、これまで定期払の際に送付していた「支払通知書」は、今回の改正に伴い廃止となりますのでご了承ください。
2 改正後の児童手当の額
| 区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |||
| 児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 | 10,000円 | ||
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 高校生年代 | 対象外 | 10,000円 | |||
| 特例給付 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
5,000円 | 該当なし(所得制限撤廃) | ||
※改正前に所得上限限度額以上で受給できなかった人は、改正後は所得制限撤廃により児童手当が受給できるようになります。
※「第3子以降」は、22歳の年度末までの監護する子をカウントし、支給対象児童が第3子以降にあたる場合に増額となります。(制度変更前は18歳の年度末までの子をカウント)
3 スケジュール
八千代市においては、下記のとおり予定しております。
| 日付 | 現在受給していない人 (新規認定請求が必要な人) |
現在受給中の人 |
|---|---|---|
| 令和6年8月末頃(8月28日に送付済) | 申請書等を送付 | 制度改正のお知らせ送付 |
| 令和6年9月2日~30日 ※1 | 申請受付 | (原則申請は不要)※2 |
| 令和6年12月13日 ※3 | 初回支給(令和6年10月分・11月分) | |
※1
申請が必要な人は、令和7年3月31日(月)(必着)までに申請すれば、令和6年10月分からの手当を遡及して支給することが可能です。令和7年3月31日(月)を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
※2
受給者が監護相当の世話をし、経済的負担をしている19歳~22歳となる年度の子がおり、その子を含めて子が3人以上いる人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。また、八千代市が支給対象児童として把握できていない子がいる場合は「額改定認定請求書」の提出が必要となる場合があります。
※3
提出期限後の提出や、記載漏れ・不足書類等の不備がある場合、支給が遅れる可能性があります。
4 制度改正に伴う手続きについて
(1) 新たに児童手当を受給できる人(申請が必要)
【該当となる人の例】
・これまで所得制限で不支給だった人
・支給対象となる子が全員高校生年代の人
新規認定請求(申請)が必要となります
(1)対象となる方には、令和6年8月28日に申請書を送付しました。
※ 受給者となるのは、対象児童の父母のうち所得の高い方となります。
※ 受給者が公務員の方、受給者が他市区町村におり子を別居監護している場合は、八千代市への申請は必要ありません。
(公務員の方は勤務先へ、受給者が他市区町村にいる場合はその市区町村へ、手続きの確認をしてください。)
※ 対象児童が施設入所している場合、父母は児童手当を受給できません。
(2)八千代市へ申請が必要な方であっても、申請書が送付されない場合があります。
(対象児童の住民票が市外にある等、公簿で確認できない場合)
申請が必要な場合は、お手数ですが申請書をダウンロードし提出または電子申請をしてください。
提出書類
申請書類は下記からダウンロード可能です。
| 提出書類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/435KB] (記載例 [PDFファイル/434KB]) |
請求者は父母のうち所得の高い方 | ◎必須 |
| 2 |
下記(1)及び(2)両方に該当する場合のみ提出 注1:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子 |
△該当者のみ | |
| 3 | 別居監護申立書 [PDFファイル/110KB] | 受給者が、監護する児童(高校生年代以下の子)と別居している場合に必要 (単身赴任やお子様の通園・通学の都合等) |
△該当者のみ |
| 4 | 戸籍の附票 | 受給者又は配偶者が、令和6年1月1日時点で日本に住民登録されていなかった場合に必要(ただし本籍地が八千代市の方は不要) | △該当者のみ |
| 5 | パスポートの写し (外国籍の方) |
外国籍の受給者又は配偶者が、令和6年1月1日時点で日本に住民登録されていなかった場合に必要 次のページの写しを提出してください。 ・「顔写真」が掲載されているページ ・令和6年1月1日に日本に住民登録がなかったことがわかる日本の出入国日のスタンプが押印されているページ |
△該当者のみ |
※上記の他、状況に応じて別途追加で書類の提出をお願いする場合があります
申請方法
下記のいずれかの方法により、申請をしてください。
※窓口の混雑を避けるため、郵送でのご提出または電子申請にご協力をお願いいたします。
持参による提出先
・市役所2階 子ども福祉課窓口 (※受付時間 午前8時30分~午後5時)
・各支所・連絡所
郵送提出先
〒276-8501
八千代市大和田新田312―5
八千代市子ども福祉課 児童手当担当 あて
電子申請による申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して電子申請することができます。
(インターネットに接続できるパソコンとカードリーダ、またはマイナンバーカード読み取りに対応するスマートフォンが必要です。)
※ 対応機種や動作環境については、デジタル庁のページ<外部リンク>をご確認ください。
※ 通信費用等はご自身での負担となります。
【ぴったりサービスのページ<外部リンク>】
提出期限
令和6年9月30日(月)
- 記載漏れ・不足書類等の不備がある場合、令和6年10月分(令和6年12月支給)以降の手当の支給が遅れる可能性があります。
- 上記を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)(必着)までの申請であれば、令和6年10月分から遡及して支給されます。 (ただし支給日は令和6年12月より後になります。)
- 令和7年3月31日(月)を過ぎてしまった場合、申請日の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
補足・注意事項
- 対象児童の住民票が市外にある場合等、公簿で確認できない場合は八千代市から申請書は送付されません。申請が必要な場合は、お手数ですが申請書をダウンロードし提出または電子申請をしてください。
- ご家族の状況によっては別途追加で書類が必要となる場合があります。【参考:児童手当のご案内ページ】
- 申請書が八千代市から届いた場合でも、受給対象とならない場合は八千代市に提出は不要です。(例:受給者が公務員、子は八千代にいるが受給者は他市町村にいる、児童が施設入所している、等)
(2) 児童手当を受給しており、手当の額が増加する人(原則申請不要)
【該当となる人の例】
・現在は所得制限により特例給付(月額5,000円)を受給している人
・中学生以下の子の他に高校生のきょうだいがいる人
・監護する子が3人以上いる人(多子加算に該当する) 等
原則、申請等の手続きは必要ありません
ただし、19歳~22歳となる年度の子を含め3人以上の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となる場合があります。 (下記「19~22歳となる年度の子を含め3人以上の子どもがいる受給者」参照)
補足・注意事項
- 八千代市が支給対象児童として把握できていない子がいる場合は、増額の申請が必要になります。
(例:市外で別居しており、これまで市に別居監護の申請をしていない高校生年代の子がいる場合等)
19歳~22歳となる年度の子を含め、3人以上の子がいる人
下記(1)及び(2)両方に該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
(1)受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担している19歳~22歳となる年度の子がいる(注1)
(2)18歳以下の児童と(1)を合わせて、3人以上の子を監護している(注2)
注1:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子
・受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担しているのであれば、子と別居している場合や、子に収入がある場合も該当します。
・生活費の相当部分とは、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合を指します。
注2:19歳~22歳となる年度の子がいても、監護する子が2人以下の場合は提出不要
「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
児童手当は、監護する子が3人以上いると、第3子以降の手当額が30,000円に増額します。この時、「第〇子」としてカウントされる子は、児童手当法で規定された子のみであり、下記の表のとおりです。
| 子の年齢 | 児童一人当たり手当月額 | 児童手当法上の子としてカウント |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 〇15,000円 (第3子以降は30,000円) |
〇 |
| 3歳~18歳の年度末まで | 〇10,000円 (第3子以降は30,000円) |
〇 |
| 19歳~22歳となる年度 | ×手当対象外 | 〇ただし、受給者が子の監護相当の世話と生活費の相当部分負担をしている時 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要(※) |
| 23歳となる年度~ | ×手当対象外 | ×対象外 |
(※)対象となる19~22歳となる年度の子がいても、子の数が3人に満たない場合は提出不要
例えば、20歳、15歳、14歳の監護する3人の子がいる受給者の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出有無により、下記のとおり14歳の子の手当額が変わることとなります。
| 監護する子の年齢 | 提出がない場合 | 提出があった場合 |
|---|---|---|
| 20歳 | (子としてカウントされない) | 第1子 (手当は対象外) |
| 15歳 | 第1子 月額10,000円 | 第2子 月額10,000円 |
| 14歳 | 第2子 月額10,000円 | 第3子 月額30,000円 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出方法
新規申請の場合と同様です。ただし「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみの場合、電子申請での提出はできません。窓口もしくは支所、郵送での提出をお願いします。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/79KB]はここからダウンロードも可能です。
(記載例 [PDFファイル/336KB])
提出期限(新規申請の場合と同様)
令和6年9月30日(月)まで
- 記載漏れ・不足書類等の不備がある場合、令和6年10月分(令和6年12月支給)以降の手当の支給が遅れる可能性があります。
- 上記を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月)(必着)までのご提出であれば、令和6年10月分から遡及して反映され、後日差額分が支給されます。
(参考)2回目以降の監護状況の確認について
19歳~22歳となる年度の子が学生の場合とそれ以外の場合で、2回目以降の確認方法が異なります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は19歳~22歳となる年度の子の状況によっては毎年提出が必要になります。
| 19~22歳となる年度の子の状況 | (1)初回の提出 | (2)2回目以降 |
|---|---|---|
| 学生 |
新規認定請求時、または19歳となる年度になった時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出 |
初回に記載した卒業見込みの月までは再提出不要。ただし、変更が生じた場合は届出が必要 |
| 学生でない | 上記と同じ | 毎年6月の現況届で再提出が必要 |
5 審査結果について
制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)は、令和6年12月6日(金)発送予定です。
※令和6年10月以降に提出があった方・不備等あった方については、審査終了後順次発送いたします。
6 よくある質問
児童手当制度全般に関することについては、こども家庭庁のページ<外部リンク>もご確認ください。
| 質問 | 回答 | |
|---|---|---|
| 1 | Q.現在児童手当を受給していますが、何か手続きは必要ですか。 | A.高校生年代の子がいる場合など、手当が増額となる方であっても、市が公簿で確認できる場合は、職権で増額の手続きを行うため、原則手続きは不要です。 ただし、19歳~22歳となる年度の子を含め3人以上の子を監護している場合や、その他公簿で確認できない場合は別途申請が必要となる場合があります。 |
| 2 | Q.現在児童手当を受給している場合、原則申請は必要ないとのことですが、後から申請が必要であったことがわかった場合、手当が受けられなくなりますか。 |
A.19歳~22歳となる年度の子を含め3人以上の子を監護している場合や、対象児童が市外にいる場合など、現在児童手当を受給している方でも申請が必要な場合があります。 |
| 3 | Q.現在19歳~22歳となる年度の子を監護していますが、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要ですか。 | A.監護相当・生計費の負担についての確認書は19歳~22歳となる年度の子を、多子加算(第3子以降の子は増額)の対象とするために必要となります。19歳~22歳となる年度の子がいても、監護する子が3人以上とならない場合は提出は不要です。 |
| 4 | Q.現在19歳~22歳となる年度の子がいますが、同居していません。監護相当・生計費の負担についての確認書を提出すれば、多子加算の対象になりますか。 |
A.同居していなくても、受給者となる父母が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担しているのであれば、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することにより、多子加算の対象となります。(なお、子どもが3人以上いない場合は、そもそも多子加算にならないため、提出は不要です。) |
| 5 | Q.申請書が送付されてきましたが、宛名が児童の保護者ではありませんでした。申請者は誰になりますか。 | A.申請書は、対象年齢の児童がいる世帯の世帯主様あてに送付しているため、宛名となっている方が受給者になるとは限りません。 受給者は、児童の父母のうち生計中心者(所得の高い方)が受給者となりますので、その人が申請をしてください。 |
| 6 |
Q.ホームページに掲載されているものとは別の申請書が送られてきましたが、何故ですか。 |
A.受給者の令和6年度所得が所得上限限度額以上となり、令和6年5月で消滅となった方に関しては簡便な形の申請書を送付しています。同封の「児童手当・特例給付 支給自由消滅通知書」もあわせてご確認ください。 |
| 7 | Q.新たに受給できるはずですが、申請書が送付されません。 | A.対象となりえる方に申請書を送付していますが、公簿で確認ができない場合は申請書が送付されません(例えば、子が市外で別居している場合等)。お手数ですが、申請書をダウンロードするか、電子申請をご利用ください。 |
| 8 | Q.公務員ですが八千代市から申請書が送られてきました。提出が必要ですか。 |
A.申請書は八千代市に住民票があり八千代市で手当を受給してない世帯に送付しています。公務員の方は、勤務先で児童手当の申請、受給することとなりますので、八千代市に申請等は必要ありません。 |