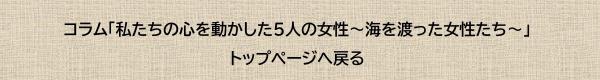本文
金子文子―コラム「私たちの心を動かした5人の女性」(5)
 金子文子(1905年~1926年)
金子文子(1905年~1926年)
両親のせいで生活も学業も翻弄される
金子文子(かねこ ふみこ)は、1905(明治38)年(※1)に、神奈川県の横浜で父・佐伯文一と母・金子きくの の間に生まれました。父と母は駆け落ちし、文子が生まれましたが、2人は入籍せず、出生届も出しませんでした。父は決まった仕事に落ち着くことがなく、夫婦仲が悪くなり、別れて暮らすことになりました。文子は勉強好きで優秀でしたが、戸籍がないため学校に通えず私塾に通うなど、両親のせいで生活も学業も翻弄されていきます。
1912年、突然父方の祖母と叔母が、文子を引き取りたいと申し出て、朝鮮の芙江(プガン)で暮らすことになりました。その生活は、小学校に行く以外は女中として家事全般をさせられるというもので、少しでも間違いがあると体罰を受けました。病死した友人の形見の裁縫箱を祖母に奪われることもありました。
パクヨルが作った詩「犬コロ」と出会う
こうした生活が7年続いた後、文子は山梨に帰されることになりました。1920年に、苦学する覚悟で大叔父を頼りに上京し、英語や数学を学ぶことになりました。「嫁に行け」という大叔父の反対を押し切って、新聞の売り子や露店商人などをしましたが、学業と両立することができませんでした。
大叔父の元で家事手伝いをしながら学校へ通う中、共産主義者や無政府主義者たちと交流し、パクヨルが作った詩「犬コロ」と出会いました。使命感を覚えた文子は、パクヨルと同棲生活を始めました。1923年に文子とパクヨルは不逞社(ふていしゃ)を設立し、『太い鮮人』『現社会』などを出版しました。
獄中で自伝を書く
同じ年の9月に関東大震災が起こると、この機に乗じて警察や軍隊が社会運動家などへの弾圧を行い、文子とパクヨルは警察に連行されました。1926年3月に皇太子暗殺の意図があったとして大逆罪(※2)で、物的証拠も無しに死刑判決が出ました。翌月の4月に天皇の名による恩赦で無期懲役になりましたが、文子は受け取った減刑状を破り捨て、7月に刑務所内で自殺しました。
文子は獄中で、原稿用紙700枚分の自伝『何がわたしをかうさせたか』を書きました。この原稿は、仲間に届けられ1931年に出版されました。文子は、幼少期から受けてきた苦難を乗り越えた生き方について書いた自伝を、社会を良くしようとしているすべての人に読んでもらいたいと考えていました。
私は、2022年に出版された小説『両手にトカレフ』を読んだとき、驚きを覚えました。イギリスで暮らす主人公である14歳のミアは、図書館でカネコフミコ(金子文子)の自伝に出会います。過酷な家庭環境に悩むミアは本を読み、フミコを身近に感じ、それが力になっていきます。文子の自伝は、願い通り次世代に力を伝えていると感じました。文子自身の青春も学ぶ目的や願いも叶ったと、私は思います。
※1 1902年(明治35年)という説もある。
※2 大逆罪・・・1947年まで存在した天皇・皇后・皇太子などに危害を加える者を死刑とする規定。
参照:『らいてう(十八)』らいてうの会編・発行、『何が私をこうさせたか―獄中手記』金子文子著・岩波書店発行、『瀬戸内寂聴全集 第六巻』瀬戸内寂聴著・新潮社発行、『両手にトカレフ』ブレイディみかこ著・ポプラ社発行、『図説日本史通覧』帝国書院発行
(M.F)