本文
八千代台図書館・公民館合同主催講座「認知症サポーター養成講座~知って安心!地域がつながる~」が開催されました
講座概要
開催日時 令和7年9月3日13時30分から15時
会 場 八千代台公民館研修室
講 師 社会福祉法人六親会
八千代市八千代台地域包括支援センター
社会福祉士・精神保健福祉士
土屋真穂氏
生活支援コーディネーター・社会福祉士
伊藤美和氏
参加人数 11人
会 場 八千代台公民館研修室
講 師 社会福祉法人六親会
八千代市八千代台地域包括支援センター
社会福祉士・精神保健福祉士
土屋真穂氏
生活支援コーディネーター・社会福祉士
伊藤美和氏
参加人数 11人
※お断り
今回のテーマは繊細な要素を含みます。また,HP中の記述は特定の意見や立場を表明したものではありません。また,可能な限り公正な記述を心掛けておりますが,完全に公正な記述とすることが不可能なテーマでもありますことを予めお断りいたします。
令和7年9月3日,八千代台図書館・公民館合同主催講座は前週の「ドキドキわくわくお話の世界」に引き続き,初の2週続きの開催となりました。今回は本来のスタイルでの講座です。9月が「世界アルツハイマー月間」であることから,本来もっと身近であることを知るべき認知症に対する正しい知識と実態を知っていただくために,八千代台公民館スタッフを中心として企画されました。
2004年に厚生労働省が「痴呆症」の名を「認知症」に改めて約20年。認知症と言う名称は国の狙い通りに浸透が進んでいるようですが,果たして様々な誤解や偏見も良き方向へと変わることができたのでしょうか。
八千代台地域包括支援センターで地域での支援活動に従事されていらっしゃる土屋先生と伊藤先生をお招きし,講話を頂戴しました。
今回のテーマは繊細な要素を含みます。また,HP中の記述は特定の意見や立場を表明したものではありません。また,可能な限り公正な記述を心掛けておりますが,完全に公正な記述とすることが不可能なテーマでもありますことを予めお断りいたします。
令和7年9月3日,八千代台図書館・公民館合同主催講座は前週の「ドキドキわくわくお話の世界」に引き続き,初の2週続きの開催となりました。今回は本来のスタイルでの講座です。9月が「世界アルツハイマー月間」であることから,本来もっと身近であることを知るべき認知症に対する正しい知識と実態を知っていただくために,八千代台公民館スタッフを中心として企画されました。
2004年に厚生労働省が「痴呆症」の名を「認知症」に改めて約20年。認知症と言う名称は国の狙い通りに浸透が進んでいるようですが,果たして様々な誤解や偏見も良き方向へと変わることができたのでしょうか。
八千代台地域包括支援センターで地域での支援活動に従事されていらっしゃる土屋先生と伊藤先生をお招きし,講話を頂戴しました。

講座の様子
数々のネガティブな印象を与える医療用語・福祉用語等は,ほんの20~30年前まで公的機関を含め,医療や福祉の専門家と言われる現場や一般的にも普通に使用されていました。1990年代後半から2000年代にかけて,厚生労働省を中心にそれらは修正されましたが,そこに至るまでの道のりは本当に長いもので,一例としてハンセン氏病を巡る歴史が有名です。
今回のテーマである認知症について,まず名称を巡る歴史を紐解くと,「痴呆症」の名は,明治時代に西洋医学が導入された当初に「Dementia」という単語が「狂ノ一種」「痴狂」といった,「狂気」の意に近い病態として訳されたことに端を発するとされています。
そこで1909年,東京帝国大学医科大学教授・東京府巣鴨病院院長であった呉秀三氏らが雑誌『神経学雑誌』に掲載の論文『精神病ノ名義ニ就キテ』において,「狂」などの文字が持つネガティブなイメージを避ける目的で「痴呆」という言葉が提唱されたとのことです。しかし,医学用語として定着し,法令でも使用されたことで一般にも広く普及した結果,皮肉にもかえって差別的な響きも含めて普及・定着してしまい,「ぼけ」という俗語などとも結びつき,一種の偏見や誤解を助長し,早期発見早期診断や適切な治療・ケアを妨げる一因になった,と言われています。
国家的な取り組みとして用語の修正を実施し,草の根の活動の努力もあり,少しずつですが,認知症への理解が実を結びつつあります。しかし,明治時代から続いた用語に対する印象を完全に払拭するには,まだ年月と努力が必要になるのかもしれません。
それはともかく,演題にもある認知症サポーターとはなにか。特別な資格の取得者ではなく,認知症の方やその家族を温かく見守り,支援する「応援者」のことです。国が推進する「認知症サポーターキャラバン」事業によって養成が行なわれており,技能や資格は不要で,誰もが参加できます。そして,サポーターの中には,地域の認知症カフェなどに参加したり,傾聴ボランティアとして活動するなど,積極的に支援に動く方も大勢いらっしゃいます。そうした方々を「チームオレンジ」として,一体感を持って頂くことで,よりやりがいを得て地域での具体的な支え合いが行なわれています。それらを講師から丁寧に講話を頂戴しました。
また,認知症の方への実際の声掛けや対応はどのように行えば良いのか。DVDを視聴しながら,実際にロールプレイングやグループワークをとおして皆さん真剣に学ばれていらっしゃいました。(余談ですが,DVD中の間違った対応例のロールプレイングは,実例では無いとはいえ,なかなか強烈で見ているだけでつらいものがあります…。)
難しいテーマではありましたが,ほのぼのとした講師のお人柄もあり,終始和やかな雰囲気で進行しました。また,たまたま地域包括支援センターで実習をされていた大学生の方も聴講され,真剣に聞き入っていらっしゃったのが印象的でした。
参加のみなさんには,図書館司書が選書した関連資料のブックリストを配付させていただきました。参加者のみなさん,土屋先生,伊藤先生,実習生のお二方にスタッフのみなさん,長時間にわたってお疲れ様でした。今後も楽しく,役に立つ講座を企画していきたいと思います。
今後とも八千代台図書館・八千代台公民館をよろしくお願いいたします。
今回のテーマである認知症について,まず名称を巡る歴史を紐解くと,「痴呆症」の名は,明治時代に西洋医学が導入された当初に「Dementia」という単語が「狂ノ一種」「痴狂」といった,「狂気」の意に近い病態として訳されたことに端を発するとされています。
そこで1909年,東京帝国大学医科大学教授・東京府巣鴨病院院長であった呉秀三氏らが雑誌『神経学雑誌』に掲載の論文『精神病ノ名義ニ就キテ』において,「狂」などの文字が持つネガティブなイメージを避ける目的で「痴呆」という言葉が提唱されたとのことです。しかし,医学用語として定着し,法令でも使用されたことで一般にも広く普及した結果,皮肉にもかえって差別的な響きも含めて普及・定着してしまい,「ぼけ」という俗語などとも結びつき,一種の偏見や誤解を助長し,早期発見早期診断や適切な治療・ケアを妨げる一因になった,と言われています。
国家的な取り組みとして用語の修正を実施し,草の根の活動の努力もあり,少しずつですが,認知症への理解が実を結びつつあります。しかし,明治時代から続いた用語に対する印象を完全に払拭するには,まだ年月と努力が必要になるのかもしれません。
それはともかく,演題にもある認知症サポーターとはなにか。特別な資格の取得者ではなく,認知症の方やその家族を温かく見守り,支援する「応援者」のことです。国が推進する「認知症サポーターキャラバン」事業によって養成が行なわれており,技能や資格は不要で,誰もが参加できます。そして,サポーターの中には,地域の認知症カフェなどに参加したり,傾聴ボランティアとして活動するなど,積極的に支援に動く方も大勢いらっしゃいます。そうした方々を「チームオレンジ」として,一体感を持って頂くことで,よりやりがいを得て地域での具体的な支え合いが行なわれています。それらを講師から丁寧に講話を頂戴しました。
また,認知症の方への実際の声掛けや対応はどのように行えば良いのか。DVDを視聴しながら,実際にロールプレイングやグループワークをとおして皆さん真剣に学ばれていらっしゃいました。(余談ですが,DVD中の間違った対応例のロールプレイングは,実例では無いとはいえ,なかなか強烈で見ているだけでつらいものがあります…。)
難しいテーマではありましたが,ほのぼのとした講師のお人柄もあり,終始和やかな雰囲気で進行しました。また,たまたま地域包括支援センターで実習をされていた大学生の方も聴講され,真剣に聞き入っていらっしゃったのが印象的でした。
参加のみなさんには,図書館司書が選書した関連資料のブックリストを配付させていただきました。参加者のみなさん,土屋先生,伊藤先生,実習生のお二方にスタッフのみなさん,長時間にわたってお疲れ様でした。今後も楽しく,役に立つ講座を企画していきたいと思います。
今後とも八千代台図書館・八千代台公民館をよろしくお願いいたします。
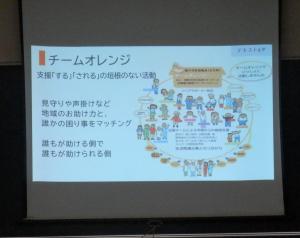




アンケートから(抜粋。すべて紹介できず,申し訳ありません。)
・今後も認知症のことについての講座があるとありがたい。
・改めて学びたい。
・サロン愛宕の内容を詳しく教えたいただきたかったです。
・もっと認知症のことをわかりやすく。
(今回,感想のご記入は少なめでしたが,講座に対しては概ね好意的な評価を頂戴しました。)
・改めて学びたい。
・サロン愛宕の内容を詳しく教えたいただきたかったです。
・もっと認知症のことをわかりやすく。
(今回,感想のご記入は少なめでしたが,講座に対しては概ね好意的な評価を頂戴しました。)
八千代台図書館がおススメする講座のポイント 「ロバ隊長」
「チームオレンジ」のマスコットキャラクターとして親しまれているその名も「ロバ隊長」。もともとは本文中でもご紹介した「認知症サポーターキャラバン事業」のマスコットとして生まれました。
しかし,なぜロバなのか?そこには「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」への先頭を歩く(だからキャラバンなのですね。),「急がず,しかし一歩一歩着実に進む」願いが込められています。
認知症サポーター養成講座の受講記念品としてロバ隊長のグッズが配布されることがありますが,介護をしていた家族を亡くしたご高齢のボランティアの方が「作り始めると夢中になって楽しい」と,月に数十個ものマスコットを作成されている例もあるといいます。また,認知症の診断を受け,普段は介助が必要な方が,子どもたちへプレゼントするロバ隊長を縫い始めると,生き生きと作業を進める姿があり,スタッフを驚かせたというエピソードもあるそうです。このように,ロバ隊長の製作は,認知症の方が「誰かの役に立っている」という役割意識や自己肯定感を持つきっかけづくりになっています。また,ロバ隊長をプレゼントされた子どもが,「これは何?」と家族などに尋ね,認知症に関する話題を広げる架け橋ともなっているのです。
一部にはロバの英単語「donkey」が「愚か者」というネガティブな意味もあると批判されたこともあるそうですが,隊長は「ロバのように忍耐強く,着実に歩みを進める取組が重要」というメッセージを送り続けています。
そして病院の受付や公共施設のカウンターなどにロバ隊長のぬいぐるみが置かれることで,「認知症にやさしい場所」「サポーターがいる場所」であることを静かに主張しているのです。
ロバ隊長は認知症に対する正しい認識を届けるための大使として,日々,これからもみなさんと共にゆっくりと歩んでいくことでしょう。
【今回の記事は,『『痴呆』に替わる用語に関する検討会報告書・資料』(厚生労働省 2004年)等および八千代台地域包括支援センターよりご提供いただいた『八千代市認知症安心ガイド~認知症の人と家族にやさしい八千代を目指して~』(八千代市 2025年),『知っておきたい脳の健康~これからのために'“今”できること~』(エーザイ株式会社 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授 同大学精神神経科・メモリー外来 診察部長 繁田雅弘 2023年),『認知症の人と家族の思いをより深く知りたいあなたへ』(公益社団法人認知症の人と家族の会),『認知症サポーター養成講座標準教材 認知症を学びみんなで考える』(全国キャラバン・メイト連絡協議会 2023年)他資料をもとに作成いたしました。ご協力ありがとうございました。】
しかし,なぜロバなのか?そこには「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」への先頭を歩く(だからキャラバンなのですね。),「急がず,しかし一歩一歩着実に進む」願いが込められています。
認知症サポーター養成講座の受講記念品としてロバ隊長のグッズが配布されることがありますが,介護をしていた家族を亡くしたご高齢のボランティアの方が「作り始めると夢中になって楽しい」と,月に数十個ものマスコットを作成されている例もあるといいます。また,認知症の診断を受け,普段は介助が必要な方が,子どもたちへプレゼントするロバ隊長を縫い始めると,生き生きと作業を進める姿があり,スタッフを驚かせたというエピソードもあるそうです。このように,ロバ隊長の製作は,認知症の方が「誰かの役に立っている」という役割意識や自己肯定感を持つきっかけづくりになっています。また,ロバ隊長をプレゼントされた子どもが,「これは何?」と家族などに尋ね,認知症に関する話題を広げる架け橋ともなっているのです。
一部にはロバの英単語「donkey」が「愚か者」というネガティブな意味もあると批判されたこともあるそうですが,隊長は「ロバのように忍耐強く,着実に歩みを進める取組が重要」というメッセージを送り続けています。
そして病院の受付や公共施設のカウンターなどにロバ隊長のぬいぐるみが置かれることで,「認知症にやさしい場所」「サポーターがいる場所」であることを静かに主張しているのです。
ロバ隊長は認知症に対する正しい認識を届けるための大使として,日々,これからもみなさんと共にゆっくりと歩んでいくことでしょう。
【今回の記事は,『『痴呆』に替わる用語に関する検討会報告書・資料』(厚生労働省 2004年)等および八千代台地域包括支援センターよりご提供いただいた『八千代市認知症安心ガイド~認知症の人と家族にやさしい八千代を目指して~』(八千代市 2025年),『知っておきたい脳の健康~これからのために'“今”できること~』(エーザイ株式会社 東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授 同大学精神神経科・メモリー外来 診察部長 繁田雅弘 2023年),『認知症の人と家族の思いをより深く知りたいあなたへ』(公益社団法人認知症の人と家族の会),『認知症サポーター養成講座標準教材 認知症を学びみんなで考える』(全国キャラバン・メイト連絡協議会 2023年)他資料をもとに作成いたしました。ご協力ありがとうございました。】











