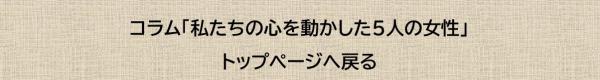本文
茨木のり子―コラム私たちの心を動かした5人の女性(1)
 茨木のり子(いばらぎのりこ)は、1926(大正15)年、医者である父・宮崎洪と母・勝との間に大阪で生まれました。弟・英一がいます。父の勤務の関係で大阪から京都、愛知県西尾へと転居。1943年に西尾高等女学校を卒業して東京の帝国女子医学薬学専門学校(現・東邦大学薬学部)に入学しました。しかし東京は爆撃を受け焼け野原となり、実家に戻ります。終戦後、再上京して観た新劇に感激し、戯曲を書いて読売新聞主催の戯曲募集に応募しました。その後、童話や数々の詩を書くようになりました。1953年、川崎洋と共に同人詩誌『櫂』を創刊しました。また、夫の死後50歳で韓国語の勉強を始めたのり子は韓国語の訳詩をして、1990年に『韓国現代詩選』を出版し、読売文学賞を受賞しました。2006(平成18)年、79歳で亡くなりました。
茨木のり子(いばらぎのりこ)は、1926(大正15)年、医者である父・宮崎洪と母・勝との間に大阪で生まれました。弟・英一がいます。父の勤務の関係で大阪から京都、愛知県西尾へと転居。1943年に西尾高等女学校を卒業して東京の帝国女子医学薬学専門学校(現・東邦大学薬学部)に入学しました。しかし東京は爆撃を受け焼け野原となり、実家に戻ります。終戦後、再上京して観た新劇に感激し、戯曲を書いて読売新聞主催の戯曲募集に応募しました。その後、童話や数々の詩を書くようになりました。1953年、川崎洋と共に同人詩誌『櫂』を創刊しました。また、夫の死後50歳で韓国語の勉強を始めたのり子は韓国語の訳詩をして、1990年に『韓国現代詩選』を出版し、読売文学賞を受賞しました。2006(平成18)年、79歳で亡くなりました。
私の心を動かすところ
のり子の父は、女性も経済的に男性に寄りかからず、自立して生きて行くべきだと考えていました。のり子に薬学を学ばせようと東京の帝国女子医学薬学専門学校に進学させます。けれども第二次世界大戦での戦況は悪化して授業どころではなく、学徒動員で働かされるうちに東京は米軍の爆撃で焼け野原になりました。のり子自身は理数が苦手で薬学も身に付かず、卒業はできたものの薬剤師として働きたくはなかったようです。戦後の東京で新劇や海外からの新しい文化に心を惹かれたのは、もともと文系志向だったからではないでしょうか。
12歳のときに亡くなった母の故郷山形県庄内地方の自然に培われた感性を自らも大事にし、縁あって祖母が見込んだ庄内地方出身の医師三浦安信と結ばれ、幸せな結婚生活を送りました。安信は、のり子の理想である藤沢周平著の「たそがれ清兵衛」に風貌が似ている、眉目秀麗で端正な庄内武士のような人物であったようです。25年間を共にした安信が、のり子が49歳の時に肝臓がんで世を去り、戦後を共有した一番親しい同志を失った感が痛切にきて、虎のように泣いたとのことです。
その後、親しい編集者に詩論を書くことを薦められ『詩のこころを読む』が刊行されました。このことで、のり子は安信を失った悲しみから立ち直ることができたようです。70代になって出版した詩集『倚りかからず』で世に広く名前を知られるようになりました。
子どもの頃に度々訪れた山形庄内地方の澄んだ空気をたっぷり吸って成長し、戦時中に青春時代を過ごし、その後思考の似た者同士であった夫と満ち足りた結婚生活を送ることができたのり子は、自分の意思を尊重して生き、まさに何物にも倚りかからない一生を送ったのではないでしょうか。私もこんな潔い生き方ができたらと、目標にしたい女性の一人なのです。
参照:『清冽 詩人茨木のり子の肖像』後藤正治著中公文庫発行
(I.K)
注記:らいてうの会は女性がどのように生きたかを重点に学んでいます。文献によって生年などの記述が異なる場合がありますが、学習のまとめとして作成している記録誌を基本としています。