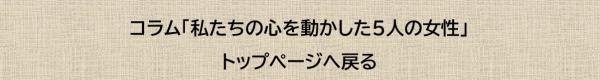本文
新島八重―コラム私たちの心を動かした5人の女性(1)

新島八重(にいじまやえ)は、幕末の1845(弘化2)年、会津藩士山本権八の娘として誕生しました。その頃、徳川幕府の力が弱まり、新しい政府を作ろうとする勢力との間に戦いが起こりました。その中で藩の学校の教授をしていた川崎尚之助と結婚します。1868年、幕府の側に立った会津藩は戦いに敗れ、夫婦は生き別れとなりました。
1871年、母たちと京都へと逃れ、一足先に京都に移っていた兄・覚馬と共に学校の先生を始めます。1876年、兄の友人の新島襄と結婚し、夫とともに同志社というキリスト教の学校創設に関わっていきます。1890年、夫が亡くなった後は看護教育に積極的に貢献し、日清・日露戦争で看護婦として従軍しました。こうした社会活動に幅広く活躍し、1932(昭和7)年、86歳で亡くなりました。
私の心を動かすところ
八重の生涯を追っていくと、東北の会津という、江戸からも、京の都からも遠い土地で育った少女が、幕末という嵐のような時代の中で、たくましく生き抜いた姿があります。父親の専門である砲術を習い、男装して会津を守るため闘った力強さに目を見張ります。
会津藩が敗れたあと、遠い京都で教師をしながら茶道を学び、兄の本の出版の手助けをしました。八重には困難に負けずに人生を切り開いていく力強さがあります。
ハンサムウーマンとは行動や態度がりりしい女性、自立した女性を意味します。夫の襄に「彼女の生き方はハンサムなのです」と称賛された八重の自立した生き方に私は心惹かれました。中でも、夫亡き後、同志社の女性教育や、看護という仕事を通して自立した女性を育てる活動に生涯を捧げたところに感じ入りました。
(O.M)
注記:らいてうの会は女性がどのように生きたかを重点に学んでいます。
文献によって生年などの記述が異なる場合がありますが、学習のまとめとして作成している記録誌を基本としています。