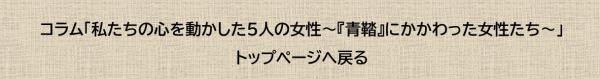本文
長沼智恵子―コラム私たちの心を動かした5人の女性(2)

長沼智恵子(ながぬまちえこ)は、1886(明治19)年、福島県安達郡由井村で父・今朝吉、母・センの長女として生まれました。智恵子は幼いときから絵が得意で学業も優秀。1903年上京、日本女子大学校家政学部へと進学して近代化の息吹に接します。寡黙でしたが活発さと意思の強さとを併せもつ彼女は在学中に絵画に目覚め、画家を志し太平洋画会研究所に通います。『青鞜』の表紙絵を描き「新しい女」と言われ、その後高村光太郎と運命的に出会います。
私の心を動かすところ
智恵子が学んだ太平洋画会研究所には、当時の新進洋画家・津田青楓(せいふう)や中村彝(つね)らが出入りしており、彼らのアトリエを訪問しては絵を見せてもらうなど、意欲的に新しい絵画を吸収していきました。当時、日本に紹介されたばかりのセザンヌやゴーガンにも夢中になりました。『青鞜』創刊にあたり、平塚らいてうの依頼をうけた智恵子が描いた表紙絵はクリーム色の地にチョコレート色で、気品のあるギリシャ風女性の立像を表し、自立した女性を目指す『青鞜』を象徴するにふさわしいものでした。
1911年の冬、友人の紹介で、彫刻家で詩人の高村光太郎に会い、たびたびアトリエを訪れようになりました。智恵子の目に光太郎は、フランスから帰国したばかりの、新進彫刻家であり、美術界の古い風習にとらわれずに果敢に戦いをいどむ、理想の男性として映りました。光太郎もまた、智恵子のなかに、「自分をしっかりもっている女」「豊かな感受性に富んだ女」、つまり光太郎の理想とした対等に話せる日本女性を発見して大いに喜びました。この頃の智恵子は『青鞜』2巻1号に花のモチーフによる表紙絵、2巻6号に「マグダに就て」の感想文、画廊で小説家・田村俊子のあねさま人形と智恵子のうちわ絵の陳列会を開くなど精力的に活動しました。俊子とは『青鞜』で知り合い、とても親しくしていました。
智恵子(29歳)と光太郎(32歳)は1914年12月に結婚し、東京・本郷駒込林町のアトリエで新婚生活を始めましたが、二人の意志で入籍はしませんでした。苦しい生活だったので、光太郎は「ロダンの言葉」「回想のゴッホ」などの翻訳をして生活の糧にしました。智恵子は結婚後も、油絵の勉強を続けますが、作品を発表することはありませんでした。智恵子は自身の制作にジレンマを感じ、それは光太郎も受け止めていました。
自身の貧しさには動揺しない智恵子も、実家の酒屋の経営難には心を痛めていました。結局、倒産。実父の永眠。その頃から精神分裂症の徴候があらわれ睡眠薬による自殺を図ります。智恵子の病状が進む中、光太郎は智恵子を入籍します。光太郎の懸命の看護にもかかわらず、1938年、南品川のゼームス坂病院で亡くなりました。
芸術と光太郎への愛に生きた人でした。ひたむきに芸術を愛した智恵子は曖昧を許さず、妥協を嫌いました。生活と芸術を突き詰める極度の緊張から精魂つきて倒れました。しかし、ゼームス坂病院入院中は、一等看護師になっていた姪のはる子に最後まで看護され、死の前年の、1年半くらいのあいだは、切り絵に創作の喜びを見いだしました。彼女が作成した切り絵、千数百点は優しさに溢れています。
参照:『智恵子抄』高村光太郎著角川春樹事務所発行、『智恵子と生きた―高村光太郎の生涯』茨木のり子著童話屋発行、『『青鞜』人物事典―110人の群像―』らいてう研究会編大修館書店発行、『らいてう(五)』らいてうの会編集・発行
(M.F)