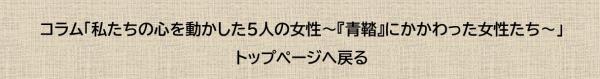本文
平塚らいてう―コラム私たちの心を動かした5人の女性(2)

平塚らいてう(ひらつからいちょう)は、1886(明治19)年、東京都麹町で父・定二郎と母・光沢(つや)の間に三女・明(はる)として生まれました。1911年に日本で初めての女性たちによる文芸雑誌『青鞜』を発行。「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった」という創刊の言葉は当時の女性たちに大きな影響を与えました。
1971(昭和46)年に85歳で亡くなりました。「生きるとは行動することである。ただ呼吸をすることではない」と女性の権利獲得のために生きた人です。
私の心を動かすところ
ペンネーム「らいてう」は信州の高い山々に住む雷鳥(らいちょう)に由来します。日本女子大学校の卒業生を中心とした『青鞜』に集まる女性たちは世間の注目を浴び、当時の社会は「新しい女」と非難しました。しかし、らいてうは自ら「新しい女」を宣言し、男性中心の法律や社会のしきたりに抵抗して人間としての権利を主張しました。
1914年、『青鞜』2月号の「独立するに就いて両親に」という私信で事実婚を発表しました。5歳年下で画家志望の奥村博(のち博史)との共同生活は話題になりました。1915年に長女・曙生(あけみ)、1917年に長男・敦史(あつぶみ)を出産し、二児の母となり、締め切り日の迫った原稿を徹夜で書いたことで乳が止まった経験から「頭脳の労働がこれほどまでに乳の分泌に影響する」と驚きました。その思いから1918年に与謝野晶子、山田わか、山川菊栄らとの母性保護論争で、働く母を社会が保護することが必要だと主張しました。働く女性と子育ての問題は今に続くものだと思います。
1919年に市川房枝らと新婦人協会を設立し、婦人の社会的地位の向上を目指して治安警察法第5条改正(※1)、花柳病(かりゅうびょう)男子の結婚制限法制定(※2)の活動をしました。健康を害したらいてうは社会活動からいったん身を引き、静養したのち1930年に成城に「消費組合我等の家」を設立しました。1941年に敦史の軍隊入隊に際し入籍して奥村姓になりましたが、「平塚らいてう」として戦後も「非武装・非交戦」を原点とした活動を行いました。1950年、講和条約の反対声明として「非武装国日本女性の講和問題についての希望要項」を来日したアメリカのダレス国務省顧問に提出します。
「新しい女」と呼ばれ、声高らかに主張する女性だと思われがちですが、実はらいてうは子どもの頃から小さい声しか出せず、演説が得意ではなかったのです。素顔のらいてうは家族を愛した物静かな女性でした。『青鞜』『婦人と子どもの権利』『女性同盟』『女性の言葉』やその他多くの論文で女性の権利を訴えたらいてう。まさに筆の力で社会に声を上げ続けた生き方に心を打たれました。
※1 婦人参政権の基礎となる
※2 花柳病・・・性病
参照:『歴史を生きた女性たち第3巻平和や自由独立を求めて』歴史教育者協議会編汐文社発行、『平塚らいてう自伝元始女性は太陽であった(上、下、完結、続編)』平塚らいてう著大月書店発行
(Y.S)