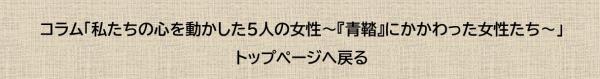本文
富本一枝―コラム私たちの心を動かした5人の女性(2)
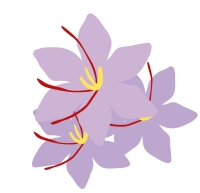
富本一枝(とみもとかずえ)は1893(明治26)年、日本画家の父・尾竹熊太郎(越堂)と母・うたの長女として富山市で生まれました。
『青鞜』の編集に携わり、尾竹紅吉という筆名で絵や文章を書き活躍しました。日本画の展覧会などでも受賞しています。富本憲吉と結婚して、一時期、憲吉の作る陶芸作品に大きな影響を与えました。
『暮らしの手帖』に、藤森清治の影絵と共に「お母さんが読んで聞かせるお話」を13年間も連載。多くの人に慕われながら、1966(昭和41)年に肝臓がんで亡くなりました。
私の心を動かすところ
父・越堂(えつどう)は、弟の竹坡(ちくは)たちとともに日本画壇で尾竹三兄弟として名をはせた画家でした。一枝は幼い頃から毎日画を描かされ、母・うたの考えでお茶や琴などのお稽古事も身に付けました。
1910年、大阪府立夕陽丘高等女学校を卒業後、東京の女子美術学校日本画選科に入学しましたが秋には中退して、心酔した平塚らいてうのもとで仲間と共に『青鞜』の編集に携わりました。それまでの女性にはないような一枝の行動は、青鞜社の活動が「新しい女」とジャーナリズムに叩かれるきっかけになります。責任を感じて青鞜社を退社した一枝は神近市子、松井須磨子や森鴎外らと共に文芸雑誌『番紅花(さふらん)』を発行しました。
その後、『青鞜』の編集が縁で知り合い、『番紅花』にも協力した芸術家・富本憲吉(東京美術学校で学び、ヨーロッパに私費留学した奈良の資産家)と恋愛し結婚しました。憲吉は、親友バーナード・リーチに影響を受けて陶芸に力を入れるようになり、一枝と共に故郷である奈良県安堵村に戻って活動します。一枝は憲吉と共に、二人の娘たちに独自の教育を実践し、また憲吉の陶芸の仕事に欠かせない助手としての役割も果たしました。常に人が集まる家でした。しかし、一枝は自分も一人の人間として仕事をしたいという気持ちを抑えられず、子どもたちの教育のためもあり、一家は東京の世田谷に移り息子も生まれました。
第二次世界大戦終戦後、憲吉は京都で陶芸作品を作り、一枝は東京に残って暮らしました。夫から生活費の仕送りは無く経済的に苦しい生活でしたが、一枝は自分の信念を貫いて、世の中の女性と子どもたちのために活動を続けました。常に周囲の人への心配りが行き届いていたそうです。1962年、新日本婦人の会結成に参加し、中央委員になりました。夫に従属せず、信念と正義を大事にした真っすぐな生き方に共感し、人間らしい愛を多くの人にたっぷり与えた女性がいたことを忘れないでいたいと思いました。
参照:『薊の花―富本一枝小伝』高井陽・折井美耶子著ドメス出版発行、『青鞜の女・尾竹紅吉伝』渡邊澄子著不二出版発行、『『青鞜』人物事典―110人の群像―』らいてう研究会編大修館書店発行
(I.K)