本文
個人市民税・県民税
個人市民税・県民税とは、毎年1月1日現在において市内に住所を有する個人にかかる税金で、定額を負担していただく「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担していただく「所得割」があります。
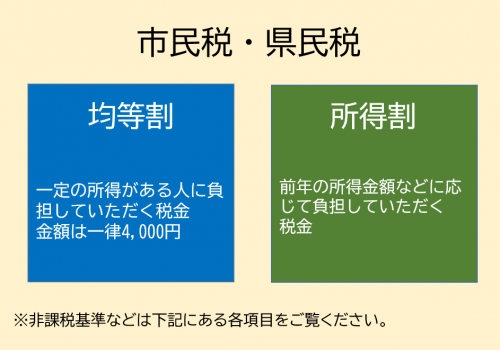
※個人県民税は、納税の利便性などのため、個人市民税と併せて徴収され、県に支払われます。
納税義務者
| 納税義務者 | 税額区分 |
|---|---|
| 市内に住所を有する個人 | 均等割と所得割 |
| 市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人 | 均等割 |
課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 本人が障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割と所得割
均等割(個人市民税・県民税)・森林環境税(国税)
| 市民税 | 県民税 | 森林環境税 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されましたので、令和6年度より均等割と併せて賦課徴収しています。
非課税基準
均等割・森林環境税は、前年中の合計所得金額が下記の金額以下の場合に非課税となります。
扶養している人がいない場合・・・415,000円
扶養している人がいる場合・・・・315,000円×(扶養人数+1)+289,000円
非課税基準(令和8年度)※令和7年1月から12月までの収入・所得
|
扶養親族の数 |
合計所得金額 |
給与収入のみの |
年金収入のみの場合 |
年金収入のみの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族なし | 415,000円 | 1,065,000円 | 1,515,000円 | 1,015,000円 |
| 扶養1人 | 919,000円 | 1,569,000円 | 2,019,000円 | 1,592,000円 |
| 扶養2人 |
1,234,000円 |
1,884,000円 | 2,334,000円 | 2,012,000円 |
| 扶養3人 | 1,549,000円 | 2,327,999円 | 2,649,000円 | 2,432,000円 |
非課税基準(令和3年度~令和7年度)
|
扶養親族の数 |
合計所得金額 |
給与収入のみの |
年金収入のみの場合 |
年金収入のみの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族なし | 415,000円 | 965,000円 | 1,515,000円 | 1,015,000円 |
| 扶養1人 | 919,000円 | 1,469,000円 | 2,019,000円 | 1,592,000円 |
| 扶養2人 |
1,234,000円 |
1,879,999円 | 2,334,000円 | 2,012,000円 |
| 扶養3人 | 1,549,000円 | 2,327,999円 | 2,649,000円 | 2,432,000円 |
※平成26年度より、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市民税・県民税の均等割を引き上げていましたが、令和5年度で終了しました。
令和5年度以前については、市民税3,500円・県民税1,500円の合計5,000円
所得割
1.収入金額から必要経費等を引き、所得金額を出します。
「収入金額」-「必要経費」=所得金額
2.所得金額から所得控除額を引き、課税対象となる所得金額(課税標準額)を出します。
「所得金額」-「所得控除」=「課税標準額」(1,000円未満切捨て)
3.課税標準額に税率をかけた後、税額控除を引き、所得割額を出します。
「課税標準額」×「税率」-「税額控除」=「所得割額」(100円未満切捨て)
【一般の所得に対する税率】
市民税6% 県民税4% 合計10%
非課税基準
所得割は前年中の総所得金額等が下記の金額以下の場合に非課税となります。
1.所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
2.扶養している人がいない場合・・・450,000円
扶養している人がいる場合・・・・350,000円×(扶養人数+1)+420,000円
非課税基準(令和8年度)※令和7年1月から12月までの収入・所得
|
扶養親族の数 |
総所得金額等 |
給与収入のみの |
年金収入のみの場合 |
年金収入のみの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族なし | 450,000円 | 1,100,000円 | 1,550,000円 | 1,050,000円 |
| 扶養1人 | 1,120,000円 | 1,770,000円 | 2,220,000円 | 1,860,001円 |
| 扶養2人 |
1,470,000円 |
2,215,999円 | 2,570,000円 | 2,326,667円 |
| 扶養3人 | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,920,000円 | 2,793,334円 |
非課税基準(令和3年度~令和7年度)
|
扶養親族の数 |
総所得金額等 |
給与収入のみの |
年金収入のみの場合 |
年金収入のみの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族なし | 450,000円 | 1,000,000円 | 1,550,000円 | 1,050,000円 |
| 扶養1人 | 1,120,000円 | 1,703,999円 | 2,220,000円 | 1,860,001円 |
| 扶養2人 |
1,470,000円 |
2,215,999円 | 2,570,000円 | 2,326,667円 |
| 扶養3人 | 1,820,000円 | 2,715,999円 | 2,920,000円 | 2,793,334円 |
申告
詳しくは、市民税・県民税の申告をご覧ください。
納税
市民税・県民税の納付方法は、下記の方法があります。
普通徴収
「普通徴収」とは、納税義務者本人が市民税・県民税を直接納付する方法です。
6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている年税額を、4期(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付します。
特別徴収
「特別徴収」とは、給与の支払いを受ける人(従業員)に課税された市民税・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所(勤務先)が毎月の給与の支払いの際に徴収(天引き)し、翌月10日までに納入する方法です。
アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、給与の支払いを受ける人は原則すべて特別徴収となります。
退職などにより、市民税・県民税を特別徴収することができなくなった場合は、未徴収税額を従業員自身が普通徴収により納付していただくか、最後に支払われる給与から一括で徴収されます。
公的年金からの特別徴収
「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市民税・県民税を徴収し、市へ納入する方法です。
65歳以上で公的年金を受給されている納税義務者は、6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている税額を、公的年金の支払者(日本年金機構など)が年6回の年金支給の際に市民税・県民税を徴収し、納入します。4月、6月、8月は仮徴収期間とし10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。公的年金からの特別徴収が初めての年度は、仮徴収期間を普通徴収(第1期および第2期)で納付し、10月より本徴収が開始となります。
詳しくは市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)をご覧ください。
個人市民税・県民税および森林環境税(国税)の減免・免除について
一定の要件を満たす場合,個人市民税・県民税は納期限の7日前までに,森林環境税は納期限までに申請することで減免・免除が受けられることがあります。個人市民税・県民税の減免要件と森林環境税の免除要件は異なります。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
八千代市個人市民税に係る減免要領
八千代市森林環境税に係る免除要領











